2019大学受験終了。戦況報告
噂には聞いていたけれど、ここまで大変とは・・・
疲れたわぁ・・・

次男の大学受験が終わり、合格発表、補欠。追加等繰り上がり発表、入学手続き、塾や学校への合否報告。そして最後の成績照会まで終わり、なんとなくぼーっと和んでいる日々。
忘れないうちに、あの激闘日々の記録を残します。
では参ります。
1)センター試験
うちは、このセンター試験で玉砕しました。今までの最低点より100点マイナスという衝撃結果。
センター試験にかける!と息巻いていただけに・・。早く受けたい!って自信満々だっただけに。
何が起こったのかわからないと、本人固まって本当に動けなくなってました。
2日間布団から出られず・・。

ショックで飲食まともにできず、時折うめき声をあげておりました。
声なんかとてもかけられなかったです。
国公立を目指す人もそうでない人も、センター試験はとりあえず受ける人多いです。うちは国立志望だったので、もちろん受験。
これが魔物でして・・・
もう来年で終わるので、今年の受験生も死にもの狂いになることでしょうね。
なにが恐ろしいって、このセンター試験、簡単そうなんですよね。問題見ると簡単で、ちょっとやったらすぐ高得点取れそうな感じ。科目数が多いので、そこが辛いところですが、それ以外は余裕・・・みたいな勘違いをさせる魔物。
しかもマーク式だし。不思議とうまくいくんじゃない?って、楽勝じゃない?って思わせる。
ところがどっこいなんだなぁ。。
こういう簡単なテストで、ミスをせずに高得点できるってのが上位層。
簡単な問題をボロボロ落として、なんでだよー!!ってなる人が多いのが現実。
そして、罠はセンター利用出願にもあります。
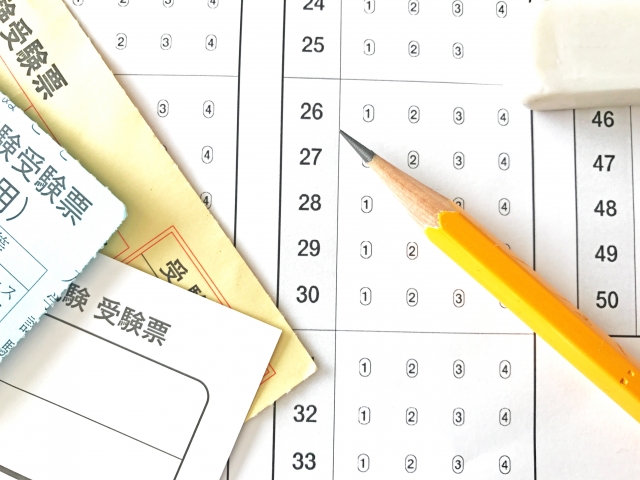
センター試験の結果だけで合否を決める私学の試験形式。これは危険だとわかっていたのに、引っかかりました。簡単な私学であっても、センター利用と呼ばれる試験方式では、レベルが跳ね上がるのです。なのになぜ受けてしまうか?
それはやはり個別に学校ごとの対策をしなくてすむというメリット。簡単そうなセンター試験の問題だけで合格できるなら、ぜひ使う!となってしまうのです。そして受験料も一般受験よりだいぶ安い!!なので親子で喜んでこれに引っかかってしまいます。
これのメリットを享受できるのは、ごくごく一部の上位層のみです。
お子さんが、東大や東工大、一橋を狙えるくらいの学力があった場合のみ有効な手段。
センター利用受験で早慶マーチレベルを抑えて、残りの時間を2次試験に費やすことが可能です。
マーチならどこか受かるんじゃないかなぁ?あわよくば早慶行けたらラッキー、みたいなレベルの人には無駄!
そのレベルだと日東駒専でも厳しいです。
たとえ「タダで出願できます」とか「1万で何個でも受験可能」と言われてもやめたほうがいいと思います。
行く気もないようなランクの学校でもどうしてもというならありですが、堅実に実力に応じた一般受験をすべき。
出願先への募金活動になってしまいます!
センター利用の甘い罠に騙されないように。
2)私大一般受験
国公立に絞ってましたが、センター惨敗で急遽私学へ切り替え。
センター利用で受けた学校はもちろん全敗。

センター利用受験は発表が遅いので、その前に出願します。センター受験後に出願できるところもあるのはありがたかったです。
この一般受験の成績というのがまたややこしく、合格最低点などの記載も「偏差点」表示が多いのです。これをよくわからないまま素点、すなわち自分のとった点数のみで判断すると「え??合格最低点超えてるのにどうして不合格??」になってしまいますので注意が必要です。
たとえば国数英の3教科受験で、合格最低点が「180点」とあったとします。これが素点であれば、そのままの点数なので、得意の数学で100点満点であれば残りの二つで40点ずつとればよいので、楽勝!ってなりますよね。
しかし合格最低点180点(偏)とあればそれは素点ではなく、偏差点、すなわち偏差値換算した点数なのです。もし数学が簡単で平均点が高ければたとえ100点満点でも偏差点はぐっと低くなるのです。基本偏差点は素点より低いと思っていた方がいいです。
全部が平均点であれば偏差点は50✖3で150点。これで最低点180と言われたら、偏差値60近くを3教科とれという話。逆に平均点が低ければ、出来が悪かったテストでも合格となります。どの学校も平均点6割くらいを目指して作るそうです。なので、素点で合格ラインを早とちりしないように。
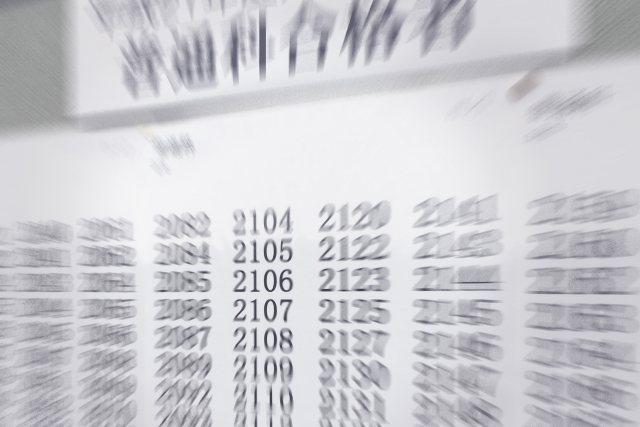

そして、学校によってですが、受験教科の組み合わせで有利不利が発生しているようです。もちろん学校側はそんな発表はしませんし、認めないでしょうけれど、受験生同士の情報交換でそういう意見が数多く見られたのは事実。これ、終わってから知る後悔といったら・・
- 滑り止め組があまり選択していない科目を選択出来るかどうかがかなり合否に関わってきます。本命組ばかりが受験している科目を選ぶだけで周りのレベルが低めの為、偏差値は上がりやすくなります。逆に滑り止め組が多く選択している科目を選ぶと、そこそこ点が取れたと思っても本命組は偏差値が低くなりがちです。(滑り止め組は満点近く普通に点が取れるから)
こういうのって、塾で教えてはくれないんですよね。
浪人生の実感レベルで、試験科目を国英社から国数英に変えて数学受験に切り替えたことろ、見違えるように合格率が上がった、などなど。どの学校にどういう傾向があるかは個別に調べないとわかりませんが、ギリギリ気味の方には貴重な情報かと思います。
3)補欠合格と追加合格
補欠って、切ない・・・
ほんの数点違いで正規合格にならずに、淡い期待を入学式まで持ち続けてしまいました。
これも動きやすい学部とそうでない学部があるようで。繰り上げ合格者一覧を見るたびため息・・
なんでここの学部はこんなにあるのに、こっちはぜろ???
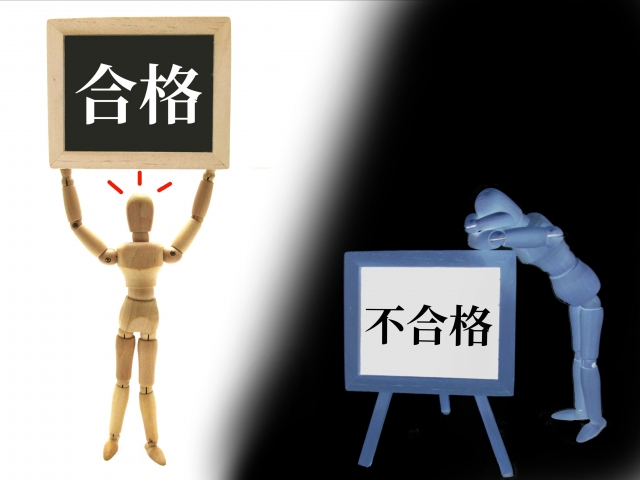
追加合格も電話が来るから、受け取れないと飛ばされてしまうとか、見落として期限を過ぎるとか・・・
何点までなら期待が持てるのか?
追加合格人数をしっかり発表してるところもあれば、そうでないところもあり。
そして合格者を絞らざるを得なかった大学側も必死で定員数を確保すべく、追加合格を続出させている背景も・・
とは言っても、自分の受験した大学の学部が今年も去年通りかなんて保証はなく、この辺も受験生泣かせなのです。
中堅以降は特に、です。

多額の入学金や授業料を収めた後に連絡をもらっても、ってのもありますしね。
ただでさえ、塾代受験代でヒーヒーなのに、最後まで余力が残せてればいいですけど・・
ちなみに。
UCAROって、受験アプリ見たいのがあるのですが、提携している大学はそこで合否発表や追加合格連絡を見ることができます。
追加合格、補欠繰り上げなどは、大学サイトで公開しているのもあれば個別に連絡くるのもありますので、UCAROも時折チェックしてました。合格発表後にくるメールは要注意。「重要なお知らせ」なーんてタイトルで送られてきたなんて話を知ってます。
必ずしも書類が届くとも限らないので、受験した学校は、発表後もよくチェックしましょう。
手続き期限切れで合格を逃した、なんて悲しいので。
4)総評
大変大変っていうけど、いつだって大変なものでしょ、受験は!
おっしゃる通りですが、ここ数年ちょっと今までと違う事情があったのです。
意外とご存知ない方も多いので、念のため書いておきます。
それは
「私立大の助成金交付」基準の厳格化
これが、中堅大以降の受験生を非常に苦しめた元凶なのです。
どういうことかというと、首都圏、大都市圏の大学に人気が集中しすぎるので、地方活性化の為に、首都圏のマンモス大学を中心に行なわれた施策。定員枠に対する合格者数の割合が一定数を超えたら、補助金のお金あげないからね、っていうもの。
これに応えて、みんなが名前を知っているような首都圏有名私大はことごとく合格者数を大幅に減少させてきたのです。


こういった定員管理の厳格化によって、今までなら合格したであろうレベルの受験生はバラバラと落ち、大学側も入るかわからない合格者をどれくらい確保すれば採算がとれるのかわからず、お互い大変な思いをしている状態。
早慶や国立といった、合格者=入学者の図式が立てやすい学校は問題ないので、難関校受験者は今まで通り。
しかし、ギリギリMARCH組~日東駒専といった併願先の学校は、どこも大変なことになったわけなのです。
関西の大学も同じ様相で、雪崩のように上から下へ、今までなら余裕だったはずの学校も、どこなら押さえられるのかで、とんでもないことに。。
そんなこんなで、国公立大を目指してましたが、結局滑り止め私学に進学することになりました。でも最後まで走りきった我が子を褒めてあげたいと思います。
合格おめでとう!

この一言がなかなか言えなかった。。
過酷な一般受験を成し遂げたあなたを、心から誇りに思っています。
お疲れさま。





